
電子レンジやマイクロ波通信は、日常生活でも必要不可欠な電子機器です。
当たり前に使っていますが、
「どうやってこの技術が働いているの?」
「事業に活用する方法はあるの?」
と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
マイクロ波は、加熱や通信以外の分野でも注目され、応用範囲が広がり続けています。
今記事では、
- マイクロ波実験装置とは
- マイクロ波の特徴
- マイクロ波の原理を活用した野菜の低温乾燥規
などについて詳しく解説します。
マイクロ波実験装置の基本概要
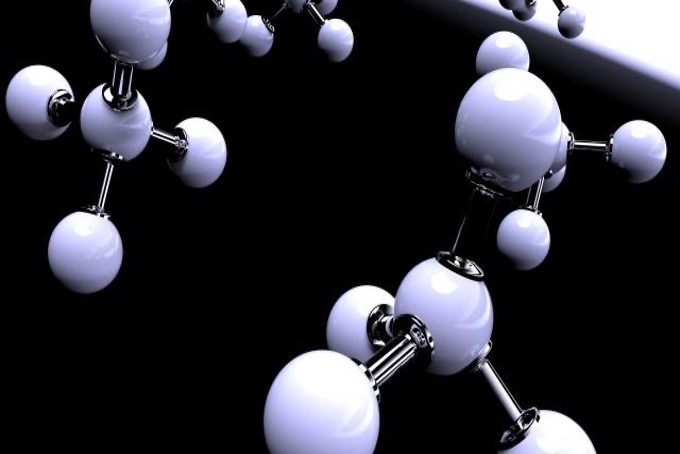
マイクロ波は、私たちの生活で欠かせない電磁波の一つとして日常に溶け込んでいますが、その仕組みについて理解している人は少ないのではないでしょうか。
ここからは、マイクロ波実験装置の基本概要と加熱原理について解説します。
マイクロ波実験装置とは
マイクロ波実験装置とは、マイクロ波の基礎学習をするために用いる装置のことです。
定在波測定、周波数測定、インピーダンス測定などができるように設計されており、マイクロ波の考え方や回路構成まで幅広い知識を身につけられます。
おもに、大学工学系学部、工業高等専門学校、工業系高校などで使われています。
通常のマイクロ波装置とは違い、電磁波を使って何かを開発したり製造したりするのではなく、あくまで基本原理を学ぶためのものです。
マイクロ波実験装置で学べる加熱原理
マイクロ波実験装置を利用すると、電磁波の一種である「マイクロ波」の加熱原理を学べます。
具体的には、周波数が300MHzから300GHzの範囲の電磁波で、分子やイオン伝導によって熱エネルギーが発生するのが特徴です。
やや難解に聞こえるかもしれませんが、電界の中にあるマイクロ波が発振した際に、物質に含まれる永久双極子(水分子など)が遅れて反応することを示しています。
遅れて反応することが抵抗力として作用して、熱エネルギーが発生して加熱するという原理です。
マイクロ波加熱の応用
マイクロ波加熱は、以下のような分野で応用されます。
- 食品分野:電子レンジ、解凍
- 化学分野:有機、無機化学反応、ナノ材料プロセス、マイクロ波焼結
- 金属分野:マイクロ波製鉄、還元
- 木材分野:木材乾燥、マイクロ波前処理
- 環境分野:水の浄化、アスベスト処理
- プラズマ分野:プラズマ励起
- 医療分野:温熱治療、ハイパーサーミア
電子レンジにマイクロ波が使われていることはよく知られていますが、それ以外にも多様な分野でマイクロ波が活用されていることがわかります。
これらは一部であり、効率性と均等性の高さを持つマイクロ波加熱は、今後も活用範囲を広げていくのではないでしょうか。
マイクロ波加熱の特性

マイクロ波加熱がここまで多くの分野で活用されているのには、ほかの電磁波とは異なる特性を持ち合わせているからです。
ここからは、マイクロ波加熱の特性について解説します。
均一な加熱
マイクロ波加熱は、内部加熱方式となっているため、短時間で物質を均一に加熱することが可能です。
従来の加熱方法では、表面から徐々に内部に熱が加わる仕組みとなっており、時間の経過とともに表面と内部では温度差や加熱ムラが発生していました。
一方のマイクロ波加熱では、物質に含まれる水分に熱エネルギーが発生するため、熱伝導に依存せずに表面と内部を同時に加熱できます。
この仕組みにより、過剰な乾燥や表面だけ焦げてしまうなどの品質問題を改善しました。
加熱効率
マイクロ波加熱は、物質に対してのみ直接的に熱エネルギーが発生するため、電界の空間や装置自体は熱を帯びません。
これにより、無駄なエネルギー消費を防いで、短時間で集中加熱するので、効率よく物質に熱を加えられるようになりました。
マイクロ波を生成する真空管の一種であるマグネトロンは、商用電源からのマイクロ波の変換効率が60〜80%とされています。
なお、915MHzのマグネトロンはそれ以上の効率が期待できるため、省エネ効果も高いです。
出力制御
マイクロ波加熱は、出力制御が簡単です。
加熱の開始、終了、停止、熱エネルギーを使っている最中の温度調整など、コントロールしながらおこなえるため、利用用途の幅広さが強みといえるでしょう。
従来の加熱方法である熱風炉は、装置を使う前の予熱時間、装置を使ったあとに冷めるまで冷却時間が必要でした。
また、加熱中に温度を変更するにしても、設定した温度に順応するまでに時間がかかっているため、出力制御という面では優れているとはいえません。
その点においてマイクロ波加熱なら、出力制御が容易なので、開発や製造における失敗リスクを軽減できます。
マイクロ波実験装置とマイクロ波装置の違い
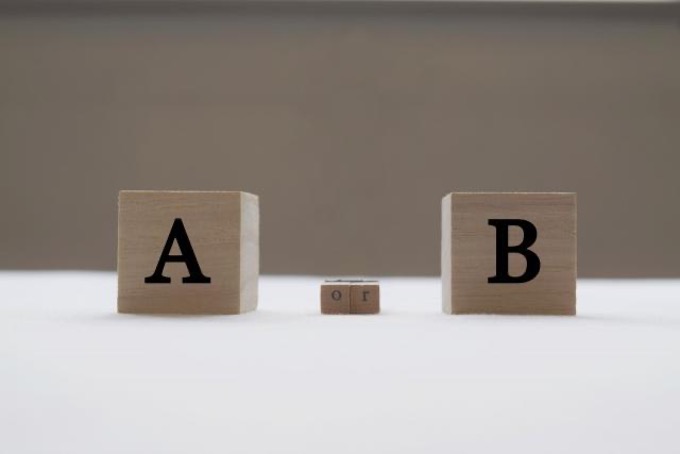
マイクロ波の実験装置と一般的な装置は、名前がよく似ているので混同されがちですが、目的が明確に違います。
ここでは、マイクロ波実験装置とマイクロ波装置の違いについて解説します。
マイクロ波実験装置
マイクロ波実験装置は、研究や実験などの目的で使われています。
そのため、装置と一緒に定在波測定、周波数測定、インピーダンス測定など複数の機材がセットになっていることが多いです。
実験装置を使うことで、以下のようなことが学べます。
- FET発振器の発振原理の確認
- マイクロ波の空間伝播及び反射
- マイクロ波の検出
- アンテナパターンの測定
- 周波数の測定
- 定在波の測定
- 管内波長の測定
- インピーダンスの測定
- インピーダンスの整合
- スミスチャートの作図法
このようにマイクロ波の原理を使った研究や実験で用いられるため、大学や研究所などに需要があります。
マイクロ波装置
マイクロ波装置は、製造プロセスの一環として使われます。
たとえば、電子レンジや産業用のマイクロ波装置のほか、新製品や新薬の開発、化学合成の加速などのために利用されています。
マイクロ波加熱の原理や特性は、多様な産業で応用するチャンスがあるため、食品業界や通信業界以外でも導入される機会が増えました。
マイクロ波の実用例

ほかの電磁波と比べても優れた特性が目立つマイクロ波、具体的にどのように使われているのでしょうか。
ここでは、マイクロ波の実用例について解説します。
野菜の低温乾燥
マイクロ波の原理を活用すると、数十度の沸点で低温乾燥と低温加熱ができます。
野菜は水や熱に弱いものが多いですが、低温で取り扱うことで、風味、色味などを破壊せずに栄養価を残したまま食品加工が可能です。
なお、乾燥したものは、離乳食や流動食の他にもスープやケーキの色付けなどにも応用できるため、アイデア次第で用途の幅はぐっと広がります。
精油の抽出
マイクロ波の原理を活用すると、物質に含まれる水分のみで熱エネルギーを生み出すので、熱や水分に弱い植物からも精油を取り出すことが可能です。
余分な水分を使わないため、精油(エッセンシャルオイル)に必要な香り成分を破壊することなく精度の高い抽出が実現します。
精油の抽出といえば蒸留抽出法が主流ですが、この方法では取り扱えない植物からも精油を製造できること、また短時間で抽出できる点において優れています。
マイクロ波を使った精油抽出に興味がある方は、こちらから詳細をご覧ください。
参考:http://kanematsu-mwextract.jp/
原子力物質の脱硝処理
専門性が高くなりますが、マイクロ波脱硝装置は、原子力業界でも実用例があります。
使用済みの核燃料は、そのまま流すわけにはいかず適切な方法で処理しなければなりません。
マイクロ波を使うことで、危険性の高い硝酸ウラニールとプルトニウム混合溶液が加熱・蒸発・分解を促して硝酸を除去できるようになります。
この仕組みによりカルメラ状の酸化物になれば、ウランやプルトニウムを再利用できる核燃料として処理が可能です。
まとめ
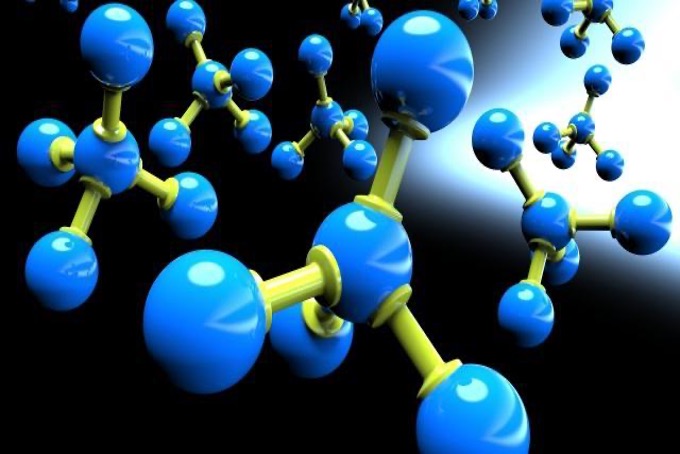
今回は、マイクロ波の実験装置について解説しました。
最後に、もう一度おさらいしましょう。
- マイクロ波実験装置はマイクロ波の原理を使った実験や研究に使われる
- マイクロ波加熱はほかの電磁波よりも均一性や効率性に優れている
- マイクロ波の原理を活用すると低温乾燥や抽出などの精度が高くなる
もし、「マイクロ波の技術を使って事業展開したい!」と思われたなら、兼松エンジニアリングへの依頼をおすすめします。
兼松エンジニアリングでは、マイクロ波を使った装置で精油や野菜・果物の低温乾燥の技術を提供しています。
興味がある方は、こちらから詳細をご覧ください。
参考:http://kanematsu-mwextract.jp/
コメントを残す