
食品ロスの問題は高い関心を集めており、企業にはSDGs達成に向けた取り組みが求められています。
実際に、日本では食べられるのに捨てられてしまっている野菜や果物がありますが、
「どのような基準で捨てられているの?」
「捨てられる野菜や果物はどのように活用すれば良いの?」
と疑問を抱く方は多いでしょう。
品質に問題のない野菜や果物を、市場に流通させたり二次利用したりすることで、SDGsを達成するだけではなく付加価値をつけて利益につなげることができます。
本記事では、
- 規格外食品とは
- 品質に問題がなくても廃棄される理由
- 規格外食品の活用方法
などについて詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みください。
規格外食品とは

「食べられるのに捨てられている食品」とは、どのようなものを指しているのでしょうか。
ここからは、規格外食品の定義や食品ロス量について解説します。
規格外食品の定義
「規格外食品」について明確な定義はされていません。
ただ、一般的にはメーカーや自治体が定めている一定水準を満たしていない食品のことで、一般に流通されずに廃棄されているものを指していることが多いです。
農林水産省が定める農産物規格に該当しない野菜や果物を「規格外野菜」、食品に限らず一定水準を満たしていない商品を「規格外食品」と区別して呼ぶこともあります。
つまり、規格外食品には、仕入れたあとの加工や梱包の過程で問題が生じ、一般に流通しない食品も含まれています。
規格外食品による食品ロス量
農林水産省が発表した食品ロス量のデータは、以下のとおりです。
| 令和2年 | 令和3年 | 前年度との比較 | |
| 食品ロス量(全体) | 522万トン | 523万トン | 1万トン増加(+0.2%) |
| 食品関連事業者から発生した食品ロス量 | 275万トン | 279万トン | 4万トン増加(+1.5%) |
| 家庭から発生した食品ロス量 | 247万トン | 244万トン | 4万トン減少(-1.2%) |
農林水産省は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)を公表し、2030年までに大幅に食品ロスを削減する方針を固めています。
ただし、現場において食品ロス量は増加しており、その半数以上は事業者から発生しています。
大幅な食品ロス削減を実現するためには、企業単位で生産や製造過程におおける食品ロス削減に取り組む必要があるといえるでしょう。
規格外食品が発生する要因
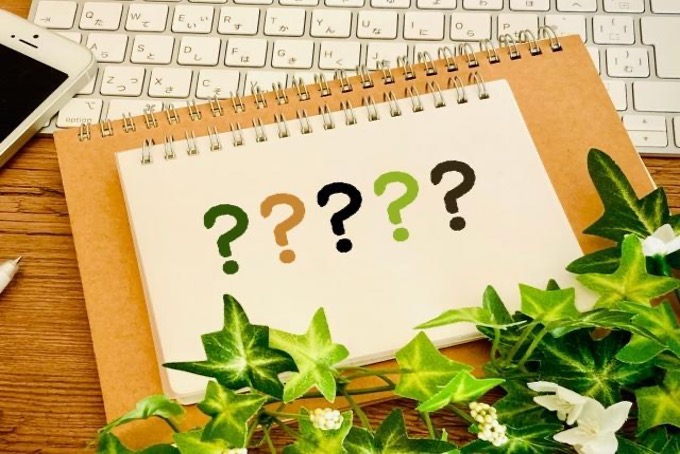
そもそも、なぜ品質に問題がなくても市場に流すことができない食材や商品がでてきてしまうのでしょうか。
ここからは、規格外食品が発生する要因について解説します。
サイズや形状が基準を満たしていない
規格外食品の大半を占めているのが、サイズや形状が基準を満たしていない野菜や果物です。
一定水準を満たしていない野菜や果物は、農家や食品メーカーの品質に対する信頼やブランドイメージの低下を招くとされています。
丸まったきゅうりとピンと伸びたきゅうりでは、ピンと伸びたきゅうりのほうが選ばれやすいのは、想像がつくでしょう。
このような消費者心理により、味や栄養価に問題がなくても厳しく基準が設けられ、その結果、捨てられる野菜や果物が増えてしまっています。
販売時期が過ぎてしまった
ハロウィーンやクリスマスなどシーズンに合わせて販売されている商品は、その時期が過ぎると、陳列棚から下されて捨てられてしまいます。
とくに、クリスマスケーキや恵方巻きなどが大量に廃棄されているニュースは、毎年のように取り上げられて、SNSを中心に議論を巻き起こしています。
焼き菓子など賞味期限の長い商品は、アウトレット商品として販売することもできますが、それでも売れるだけの生産に留める意識改革が必要です。
梱包時にミスがあった
品質や製造に問題がなくても、外装や印字にミスがあると、トラブルになるので市場に流れなくなります。
過去には飲料メーカーが商品名の印字ミスを犯し、商品が大量に廃棄される寸前でしたが、消費者の理解を得て販売されたという事例があります。
商品名の印字ミスは消費者に説明をして対処できますが、原材料や消費期限・賞味期限の印字ミスは致命的であるため、一般に流通させることはむずかしい場合が多いです。
規格外食品を廃棄しないための取り組み

食べられる商品がさまざまな理由で市場に出回らずに捨てられてしまっている現状は、どのように改善できるのでしょうか。
ここからは、規格外食品を廃棄しないための取り組みについて解説します。
SDGs理解を広げる
SDGsとは、持続可能な社会を維持するための目標を指しており、その中に食品ロスに関連する項目も含まれています。
11項目のうち3つ目の項目が「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」となっています。
世界規模で取り組まれている活動を普及させることで、世界の飢餓問題や食品ロスに伴う生産者の課題や廃棄コスト、環境問題について消費者の理解を深めることを目指す取り組みです。
生産や梱包のプロセスを見直す
もし、生産から梱包のプロセスで廃棄される商品が多く発生しているのであれば、その原因を特定して改善策を講じることが求められます。
人為的なトラブルが慢性的に起きているのであれば、従業員の研修やトレーニングをすることで軽減できるでしょう。
また、自動化システムによる不具合がある場合、商品との相性が悪い可能性があるので、開発や技術の見直しをすることで、食品ロスを削減できます。
フードバンクなどに寄付する
フードバンクとは、福祉施設や子ども食堂など貧困で悩む人たちに無料で食材を提供する団体を指します。このような団体に規格外食品を引き取ってもらうのです。
味や栄養価に問題がないにもかかわらず見た目の問題で一般に流通させられない場合、廃棄するのではなく寄付するという選択肢があることを知らない方も多いでしょう。
フードバンクの活動をおこなっているのはNPO団体であることが多いですが、このような活動に貢献することは、農林水産省も推奨しています。
農林水産省の「フードバンク」ページに、寄付できる団体が270箇所以上掲載されているので、どこに回せば良いかわからない場合は、参考にしてみてください。
規格外食品の活用方法

捨てられる商品に付加価値をつけることで、食品ロスが削減できるだけではなく、生産者の収益安定化にもつながるなど多くのメリットがあります。
ここからは、規格外食品の活用方法について解説します。
別の食品への加工
食べられるのに捨てられてしまう野菜や果物は、お惣菜やスムージー、粉末調味料など別の食品に加工することで、付加価値をつけて販売できます。
商品開発や生産環境の整備など準備するべきことは多くなるものの、規格外食品を使っていることをアピールすれば、企業のブランドイメージ向上にもつながるでしょう。
マイクロ波を利用した抽出技術を使えば、野菜や果物から有効成分だけを抽出してトマトジュースやソースなどを簡単に作ることができます。
マイクロ波を利用した抽出技術に興味がある方は、こちらから詳細をご確認いただけます。
参考:http://kanematsu-mwextract.jp/
食品以外への加工
食べられるのに捨てられてしまう野菜や果物は、別の食品に加工するほか、ヴィーガンレザーや精油などに加工することで、付加価値をつけて販売できます。
ヴィーガンレザーに関しては、動物の皮を使っていないので、サステナブルや動物愛護に関心の高い消費者に注目してもらいやすいです。
具体的に規格外食品を使っているストーリーを伝えることで、より消費者の購買意欲を刺激するマーケティング効果も期待できます。
精油に関しては、物質に含まれる水分で低温加熱する、マイクロ波を利用した抽出技術を使うことで、熱や水に弱い植物の有効成分を抽出できます。
精油抽出に興味がある方は、こちらから詳細をご確認いただけます。
参考:http://kanematsu-mwextract.jp
まとめ

今回は、規格外食品について解説しました。
最後に、もう一度おさらいしましょう。
- 品質に問題がなくても大きさや形、梱包プロセスでの問題により捨てられる食材がある
- 捨てられる食材や商品には加工することで付加価値をつけられる
- マイクロ波を利用した抽出技術で精度の高い加工が可能である
もし、「捨てられてしまう野菜や果物を使って加工食品や、精油などを作りたい!」と思われたなら、兼松エンジニアリングへの依頼をおすすめします。
兼松エンジニアリングでは、マイクロ波を利用した抽出装置を取り扱っており、捨てられてしまう食材に付加価値をつけた商品の開発が可能です。
興味がある方は、こちらから詳細をご覧ください。
参考:https://kanematsu-mwextract.jp/
コメントを残す