
「蒸留」という言葉を聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
お酒づくり?アロマオイル?それとも化学実験でしょうか。
実は私たちの身近にある香水やアロマオイル、お気に入りのウイスキーや焼酎も
すべて「蒸留」という神秘的な技術によって生み出されています。
驚くことに、蒸留技術の歴史は紀元前3500年にまでさかのぼります。
現代のような精密機器がなかった時代から、人々はさまざまな素材から、香りや油分を抽出する知恵を持っていたのです。
蒸留を行う際の方法の選択が企画や製品の命運までも左右してしまうという認識はあるでしょうか。
本記事では「常圧蒸留装置って何?」という基本的な疑問から、減圧蒸留との違い、それぞれの特徴まで分かりやすく解説します。
蒸留に興味を持ち始めた方、すでに経験がある方も読み終わる頃には蒸留の世界への理解が深まり、自分の目的に合った装置を選ぶヒントが得られるでしょう。
【常圧蒸留装置】とは

「あのブランデーの香りは何が違うんだろう?」
「手作りアロマオイルを作るにはどんな道具が必要なの?」
「DIYで自分だけの香水を作れたら素敵だな」
と思ったことはないでしょうか。
実は、あなたの身の回りのさまざまな製品には「蒸留」という技術が隠れています。
その蒸留を行う際のスタンダードな装置が【常圧蒸留装置】です。
テレビで見られるような化学実験の映像において、複雑な組み合わされたガラス管と丸いフラスコがつながったセットが常圧蒸留装置の一種です。
蒸留装置の基本を知ることで
香りの世界、お酒の味わい、さらには化学の面白さまで
新しい扉が開けるかもしれません。
「蒸留」とはそもそも何なのか?
蒸留とは、液体の中から異なる沸点を持つ成分を分離・精製するプロセスのことです。
液体を加熱して気化させた後、冷却して再び液化させることで成分を分離します。
例えば、水とアルコールの混合物では、
アルコールの沸点は約78℃、水の沸点は100℃です。
この混合物を加熱すると、まずアルコールが蒸発します。
その際に発生する蒸気を冷却することで、アルコール濃度の高い液体を得られます。
蒸留は実験室での化学分析から、石油製品の製造、
焼酎やウイスキーなどの酒類生産、アロマオイルの抽出に至るまで、
さまざまな分野で活用されているのです。
【常圧蒸留装置】は通常の大気圧で蒸留を行う装置
常圧蒸留装置は通常の大気圧(約1気圧)の環境で蒸留を行います。
加熱部、蒸留塔、冷却器、受器などの基本的な構成要素から成り立ち、
原料を加熱して発生した蒸気を冷却して液体を回収するのです。
蒸留塔は、具材を選別する様子から
トッピング装置(トッパー)とも呼ばれており、
工業的には原油の精製プロセスで広く使用されています。
石油コンビナートで見られる大きな塔がトッパーです。
ガソリン、ナフサ、LPG、灯油、軽油など
身近な石油製品は全て、原油から分離されています。
常圧蒸留装置は実験室での化学分析、酒造り、アロマセラピーのための精油抽出など、さまざまな分野で活用されています。
天然素材から香り成分を抽出する際には、素材の特性に合わせた蒸留方法で行うことが不可欠です。
常圧蒸留装置はシンプルな構造で扱いやすいため、基本的な蒸留方法として広く普及しています。
【常圧蒸留装置】の起源
蒸留技術の歴史は紀元前3500年頃のメソポタミア地方にまでさかのぼります。
初期の蒸留装置は粘土や青銅製でしたが、基本原理は現代のものと同じです。
古代エジプトでは香料や薬用成分の抽出に使われ、
8世紀頃にはアラビアの錬金術師がガラス製蒸留装置の原型を開発しています。
その後16~17世紀のヨーロッパでは蒸留技術が発展し、ブランデーやウイスキーなどの蒸留酒生産が盛んになりました。
当時は、ブドウをはじめとする農作物の冷凍保存ができない時代です。
中長期的な作物の有効活用には、蒸留酒生産が必須だったといえます。
こうした背景から常圧蒸留装置の基本設計が確立されたのです。
【常圧蒸留装置】と【減圧蒸留装置】の違い
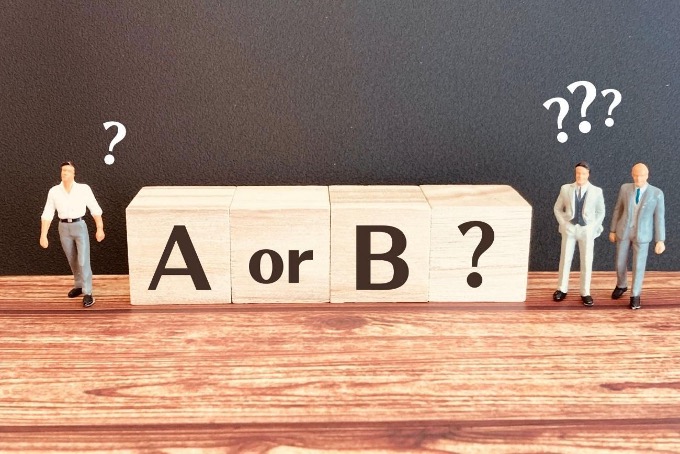
常圧蒸留装置はスタンダードなものですが、「熱で成分が変質してしまった」「高品質な抽出物を得るために最適な装置なのかが分からない」といった経験や悩みを持つ方も多いでしょう。
実は、蒸留を行う際は多くの研究者や製造者が装置選びに失敗し、期待通りの品質を得られずに困っている現実があるのです。
そんな課題を解決する可能性を持った装置が【減圧蒸留装置】です。
常圧蒸留と減圧蒸留それぞれの特性を理解して自身の目的に最適な方法を選んでいきましょう。
「減圧蒸留」の登場!きっかけは1654年の真空ポンプの発明
「富士山の頂上ではお湯が沸騰しても熱くない」
という話を聞いたことはないでしょうか。
標高3,776mの富士山頂では気圧が平地の約3分の2になり、
お湯の沸点は約87℃まで下がります。
「圧力が下がると沸点も下がる」という現象を利用したのが減圧蒸留です。
この画期的な技術は、1654年にドイツの好奇心旺盛な市長、
オットー・フォン・ゲーリケの発明品が発端です。
彼が発明した真空ポンプは当時としては革命的で、
有名な「マグデブルクの半球」実験では、2頭の馬でも引き離せないほどの真空の力を証明して人々を驚かせました。
真空ポンプの発明をきっかけに、
科学者たちは「液体を減圧状態に置いたらどうなるのか?」と実験を始め、減圧状態に置いた水や酒などの液体が、通常よりもずっと低い温度で沸騰することに気が付きました。
これは熱に弱い素材から香りや成分を抽出するのに革命的な発見だったのです。
例えば、デリケートな花から香りを抽出するとき、
常圧では100℃近い温度となるため、花の香りが変質してしまいます。
しかし、減圧環境では60℃程度で抽出できるため、
まるで生花そのものの繊細な香りを閉じ込めることが可能になりました。
【減圧蒸留装置】は香水製造、酒造の世界を一変させたのです。
【常圧蒸留装置】と【減圧蒸留装置】それぞれの仕組み
常圧蒸留装置は加熱源、蒸留フラスコ、冷却器、受器から構成されています。
原料液体を入れたフラスコを加熱すると、沸点の低い成分から順に蒸発し、
冷却されて液体として回収されます。
実験室ではガラス製の装置を用いるのが一般的です。
一方、減圧蒸留装置にはこれらに加えて真空ポンプや圧力計が必要です。
装置内の圧力を下げることで液体の沸点を下げ、低温で蒸留を行います。
装置の強度と密閉性が重要ですが、高精度なステンレス容器の製造が
近年の減圧蒸留装置の普及に火をつけました。
「常圧蒸留」と「減圧蒸留」それぞれのメリットとデメリット・抽出成分の香りや味の違い
「常圧蒸留」のメリットは、装置がシンプルで操作が容易なことです。
特別な機器が少なく初期コストも低いため、小規模な実験や生産に適しています。
しかし、高温で抽出を行うため熱に敏感な物質では分解や変質が起こりやすく、
沸点差が小さい物質同士の分離効率も低めです。
一方で「減圧蒸留」の最大のメリットは低温で蒸留できることです。
熱に敏感な物質の分解を防ぎ、沸点差が小さい物質も効率的に分離できます。
難点は、真空環境を作るために装置には複雑で精密性追加が求められる点です。
また、さまざまな機器も必要になるので初期コストが高く、操作にも技術と経験が必要です。
常圧蒸留と減圧蒸留では、抽出成分の香りや味にも大きな違いがあります。
例えば焼酎の場合
常圧蒸留では原料の香りやくせが強く出て芳醇な風味になり、
減圧蒸留ではスッキリとした淡麗な飲み口となるのが特徴です。
アロマオイルでも、常圧蒸留は原料植物の力強い香りが特徴です。
一方で、減圧蒸留では繊細でナイーブな香りが保存されます。
熱に弱い成分を含む植物では、減圧蒸留の方が質の高いオイルが得られるでしょう。
「蒸留装置」についてお悩みなら兼松エンジニアリングの【減圧蒸留装置】を

蒸留技術は古くから人類の発展に貢献してきた重要なプロセスです。
常圧蒸留装置は歴史的に重要な役割を果たしてきましたが、
熱に敏感な物質の処理や高品質な抽出には減圧蒸留が適しています。
しかし従来の減圧蒸留装置は複雑で維持管理が難しいという課題がありました。
そこで注目したいのが、
兼松エンジニアリングのマイクロ波を使用した減圧抽出装置です。
この装置は、従来の減圧蒸留の利点を維持しながら操作が容易で維持管理のしやすさも実現しています。
マイクロ波加熱技術により、効率的かつ均一な加熱が可能となり、抽出時間の短縮とエネルギーコストの削減を可能にしています。
蒸留技術の選択に悩まれている方は、
ぜひ、兼松エンジニアリングの減圧蒸留装置の導入をご検討ください。
https://kanematsu-mwextract.jp
最新の技術で、あなたの研究、製品開発をサポートいたします。
コメントを残す