
近年、食品ロス削減への関心が高まる中で、「規格外野菜」の活用は重要な要素の1つです。
規格外野菜を適切な方法で活用することで、環境負荷の低減や新たなビジネスチャンスにつなげることができます。
この記事では、規格外野菜の活用方法やそのメリット、実際の成功事例を紹介します。
規格外野菜とは

規格外野菜とは、市場で販売するための基準に適合しない野菜を指します。
通常、形や大きさ、色に不均一が見られるため、流通に乗せることができません。
これにより、多くの規格外野菜が廃棄されるという現状があります。
廃棄されてしまうのは、形が曲がっている、色が淡すぎる、サイズが規定外である、などが理由です。
しかし、これらの野菜には多くの栄養素や美味しさが詰まっており、活用する方法が求められています。
規格外野菜が生産される背景と問題点

農作物には市場での流通を円滑にするために「規格基準」が設けられています。
形や色などの外見的な要素に基づき、消費者や流通業者が一定の品質のものを受け取れるようにするためです。
スーパーに並ぶ野菜の見た目がほぼ同じなのは、この基準による選別の結果です。
規格外野菜が生産される背景
農作物には、市場で流通させるための厳密な規格基準が設けられています。
この基準に合致しないと、売れ残るか、廃棄される運命をたどることが多いです。
規格外野菜が生まれる背景には、農業の生産過程で避けられない不均一性が関係しています。
天候や病害虫の影響、品種特性、機械収穫などの要因で、同じ種類の野菜でも形や大きさに差が生じてしまいます。
この不均一性は避けられないことですが、消費者の目線では、見た目の美しさが重視されるため、基準に合わない野菜は売れにくく、結果的に廃棄されることが多いのが現状です。
規格外野菜の問題点
規格外野菜には、以下のような問題点があります。
● 見た目が悪く、消費者の購買意欲が削がれるため、無駄に破棄されてしまう
● 販売コストにばらつきが出る
● 市場価格に影響する
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
規格外野菜は形が不揃いであったり、色が均一でなかったりするため、見た目が悪く、消費者の購買意欲が削がれる可能性があります。
そのため、店頭に並ぶ前に破棄されてしまい、消費者の目に触れることなく市場から消えることも少なくありません。
また、規格外野菜は見た目の美しさや大きさが規格に合わないため、通常の価格で販売するのが難しく、安く売られることも多々あります。
このため、農家や販売者にとっては販売コストが予測できず、利益を得るのが難しくなってしまうのです。
さらに問題なのが、規格外野菜が多く廃棄されてしまうと、結果として市場に出回る野菜の供給が少なくなるため、市場価格にも影響を与えてしまいます。
需給バランスが崩れることによって、他の野菜の価格が変動したり、規格に適応した野菜が高騰したりする原因にもなるのです。
規格外野菜を活用するメリット

規格外野菜を活用することで、ゴミが減るだけでなく、環境や企業にとってさまざまなメリットがあります。
規格外野菜を活用すると、どのようなメリットに繋がるのかを詳しく紹介します。
環境面での貢献
規格外野菜を有効活用することで、食品ロスが減り、環境に対する負担が軽減されます。
世界的に食品ロス問題が注目されており、廃棄される食材を減らすことはSDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献する重要なステップです。
経済面での効果
規格外野菜を利用した新たなビジネスモデルが生まれることで、農家の収益が増加します。
例えば、加工品としての商品化や、新たな事業としての展開によって経済効果が期待できるでしょう。
そうすることで農業が発展し、野菜のさらなる品質向上にもつながります。
企業のブランディングにつながる
企業にとって規格外野菜を活用することは、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として重要です。
SDGsへの貢献や、社会貢献活動を通じて企業のブランドイメージを向上させることができるため、消費者からの信頼を得やすくなります。
また、規格外野菜を積極的に活用する企業は、環境意識の高い消費者層をターゲットにしやすくなるでしょう。
規格外野菜の活用方法

規格外野菜は、実はそのまま売る以外にも、さまざまな活用方法があります。
意外な規格外野菜の使い道もあるでしょう。
ここでは、そのまま売る以外の規格外野菜の活用方法を詳しく紹介します。
加工品としての活用
規格外野菜は、ジュースやスムージー、スープ、ピューレ、ソース、ジャムなど、さまざまな加工品に転用できます。
例えば、野菜ジュースにすることで、見た目にこだわらず栄養価を生かした製品に生まれ変わるのです。
また、冷凍食品や缶詰として保存することで、長期間活用することも可能です。
その他の用品への加工
規格外野菜を食べ物以外にも活用する試みが増えてきています。
例えば、野菜の皮を使ったバッグやクレヨンなどの製品がつくられています。
食べられない規格外野菜も有効活用できるため、より環境への配慮や経済面での貢献にもなるでしょう。
規格外野菜を活用した事例

規格外野菜の可能性に、現在多くの企業が注目しています。
大手企業も次々と規格外野菜を活用した新たなビジネスに乗り出しています。
ここでは、企業の規格外野菜を活用した成功事例を2つ紹介しましょう。
1.JTB
大手旅行会社のJTBは、食品ロス削減のため、新たなプロジェクトを始動しており、その一環として規格外野菜を活用した「ロス旅缶」を開発しました。
「ロス旅缶」は「SDGsに積極的に取り組むホテルや旅館、レストランが考案したレシピ」と、本来は廃棄される規格外野菜をJTBがマッチングさせ、缶詰へと生まれ変わらせる、というプロジェクトです。
これにより、食品ロスが削減できるだけでなく、消費者も手軽に一流シェフが作成したレシピを楽しめます。
缶の種類も非常に豊富で、ギリシャ料理やインド料理など、世界各国の料理が手軽に楽しめる非常に魅力的なプロジェクトと言えるでしょう。
2.千代田組
産業インフラや社会インフラを担う千代田組は、規格外野菜を活用した「ピューレプロジェクト」(Purée Project)を行っています。
「ピューレプロジェクト」は、最新技術を活かし、規格外野菜やフルーツを加工してピューレにする「ピューレ受託製造」や、ピューレづくりをするための「製造機器の提案」を通して、規格外野菜のロス削減に取り組むプロジェクトです。
つくったピューレは、ドレッシングやジャムなど、さまざまな食品に生まれ変わらせることができ、農家の支援や地方創生にもつながるプロジェクトとして注目されています。
規格外野菜を活用するなら兼松エンジニアリング株式会社のマイクロ波抽出装置がおすすめ
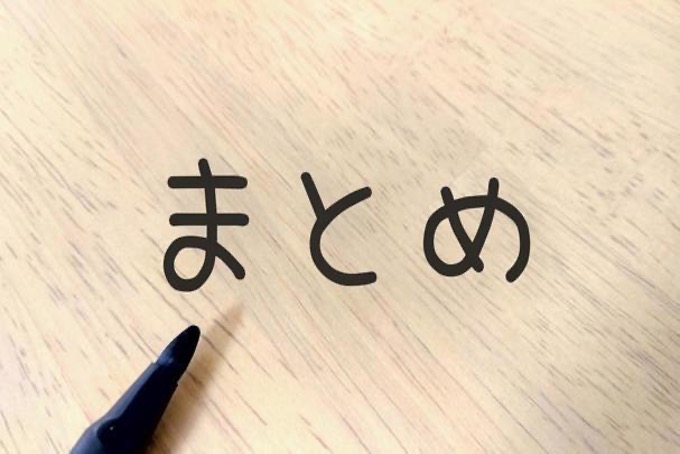
格外野菜は、見た目が規格に合わないという理由だけで廃棄されることが多いですが、適切な活用方法を導入すれば、食品ロス削減や新たなビジネス機会の創出につながります。
特に、兼松エンジニアリング株式会社のマイクロ波抽出装置を活用すれば、規格外野菜の成分を効率的に抽出し、高品質な製品として生まれ変わらせることができます。
規格外野菜の可能性を最大限に引き出し、持続可能な社会の実現に貢献するため、興味のある方はぜひお問い合わせください。
コメントを残す